 引き寄せ
引き寄せ アスタリフトCMソング2018秋 ナチュラルウーマン
今年、2018年秋。
富士フィルムアスタリフトのCM、ご覧になりましたか?
とっても素敵です。誰が美しいとかそういうことではなく、バックに流れている歌もいいし、シンプルなんだけど、シンプルさを生かす構成、私は好きです。
...
 引き寄せ
引き寄せ  私の好きな歌
私の好きな歌  引き寄せ
引き寄せ  引き寄せ
引き寄せ 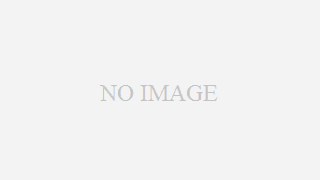 お役立ち
お役立ち  未分類
未分類 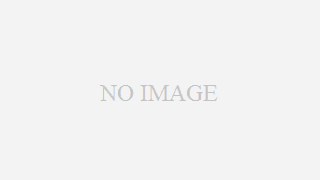 私の好きな歌
私の好きな歌  私の好きな歌
私の好きな歌  お役立ち
お役立ち 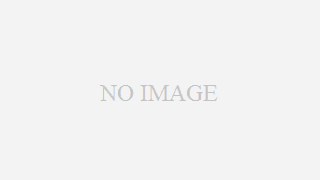 お役立ち
お役立ち